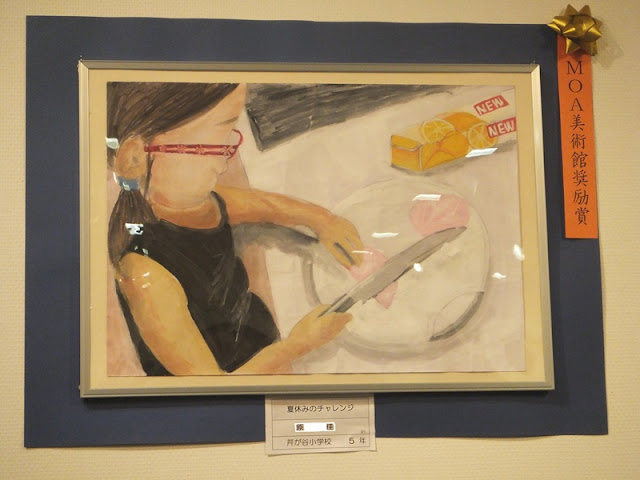一般の人もそうですが、目黒君の使い方も・・・実は時々俺もですが・・・
切れる庖丁だと物を切るときに最初だけ庖丁を動かして、切れ始めると
真下に下ろすだけ・・・トマトなんか切れにくい皮が切れると後は包丁を動かさないで
切りませんか? 皮だけ切れれば切れてしまうから、後は斧の使い方ではないですか?
切れ終わる前に庖丁の刃で切らない・・・・
目黒来んの包丁も本人が一生懸命砥いでるので、刃を動かさないでも人参が
切れています。なので解りづらいのですが、刃が垂直に動くだけなんで斧の動きです・・・
僅かながらも自分の切り方は、包丁の刃を動かして切っています。動かしているというより
刃が切っているところが変わってるように見えませんか?
皆さんが切れなくなったと感じる包丁でも刃を動かすと割と切れるんです。
ココがポイントでして皆さんが刃先を薄くしてしまう原因で早く切れなくなると感じるのでは?
こうなると、どんな包丁でも刃先を細くする・・・欠ける原因になるのだと感じるのですが?
家庭では、小さい牛刀か三徳一本で切る作業をすると歯の全部を同じに細く砥ぐと
一見、キレが良くなりますが・・・硬いものを切ると刃が欠けます・・・では刃のどの部分かと
言うと顎・・根元に近いところ・・・包丁の先の方で力を入れて切る人はいないと思うのですが
欠けずに切れる包丁にしたければ・・・家庭用とか出刃は、包丁の根元は斧、真ん中は
牛刀、先はペティーのイメージで砥ぐと一本だけでも欠けず切れる包丁の砥ぎになると
感じるようです。プロは何本もの包丁を使い分けて使うのですが若干なれどそういう
研ぎ方をします。欠けるとその分全体に研ぎ直しするので早く寿命が来てしまいます。
倍率30倍ぐらいでしょうか?図分の極上牛刀のはの拡大画像です。細かく刃がノコギリのように
刃がなっているのがわかると思います。ノコギリで木を叩いて切る人はいないでしょう?
包丁の刃も叩くとノコギリ状態の刃が潰れて切れなくなります。普通に切っていくとこのノコギリ
状態も丸くなって切れなくなります。 ハガネとステンレスはハガネの方が長斬れすると感じるのも
この辺の金属の性質なんです。ハガネは少しづつ物を切っていくと削れて行くというか?
極小さく剥がれていく・・・ステン系は剥がれず丸くなる・・・なのでステン系は切れなくなると
ツルツルして切れない感覚になるんだと思います。なので本当にうまく1万以上の砥石で砥ぐと
最初からツルツルで切れない状態になっている時があると思います。ハガネが砕いた石の集まりと
するとステン系は丸い石の集まりと考えると理解できるでしょうか?モノの例えとしてですが・・・
同じ砥石で同じ研ぎでも材質が違うので、同じ切れにするのには少しのテクニックが有るんです
これは安い包丁でも高い包丁でも材質によって研ぎ替えると切れる包丁になるんですよ。
高橋の包丁は何故良いか・・・ステン系の金属をハガネの上等な金属と同じようにする為に
強力な鍛造をきめ細くやるので金属の密度が上がるからなんです。手でハンマーを叩くぐらいでは
ステン系金属は密にならないそうです・・・ここまで叩ける機械に改造したから出来るものでして
出来なかったメーカーはステンは叩いても意味が無いという訳です。なので高橋のステン系の
包丁も欠ける・・・ただし小さく欠ける・・・これがハガネだと大きく欠けるの違いでして
本焼きのハガネの良い物は大きく欠けるので扱いが難しいのだと考えています。ステンレスの
場合、粘りが元々有るので欠けないのですがね・・・・凍った物を切れると高橋は宣伝していますが
ステン系はこの性質が有るので粘りで刃が欠けない・・・にくい・・・ハガネの性質は温度が低いと
欠け易いのではなく金属の添加物が入ってないのでつなぎ止めないので欠けると理解してくれると
小学生でも解ると思えます。ピュアな和包丁は寒い冬の朝に冷たい時には包丁砥はしない・・・
これも昔からの常識でしてうんと寒い所では包丁が鳴くんですよ・・・
また、話が飛び過ぎましたが・・・包丁は刃を動かして斬る道具です。